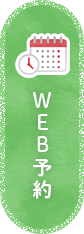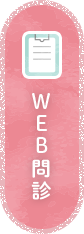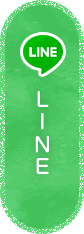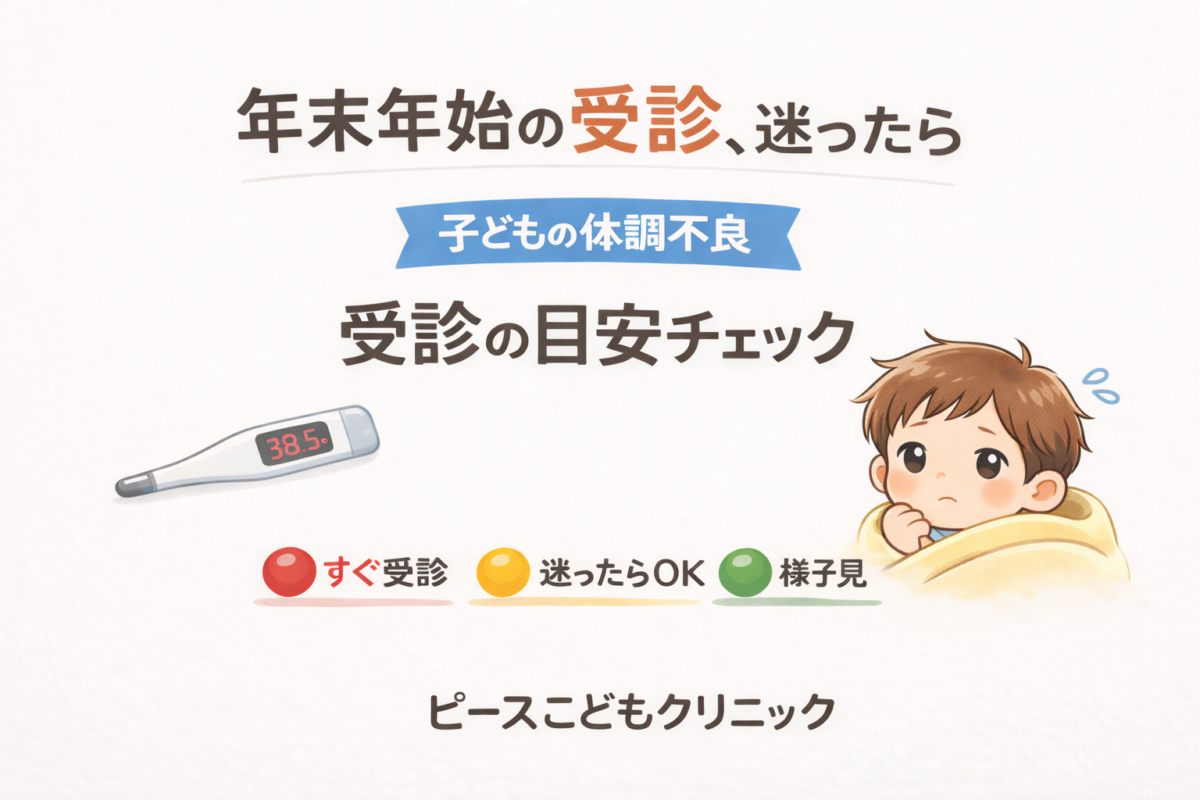こんにちは、院長の松村です。
当院では本日8月25日から、インフルエンザワクチンの予約を開始しました。昨年から鼻腔噴霧型のワクチン (フルミスト) が日本国内でも流通し、接種できるようになりました。“痛みもなくて1回だけで済む!” というと、お子さんにとって負担の少ないワクチンでとても魅力的ですよね。でも一体どのようなワクチンなのか、注意すべきことはあるのか気になっている方もいらっしゃると思います。10月2日からインフルエンザワクチン接種が始まりますが、その前にワクチンについて少し説明をしたいと思います。
大前提として、インフルエンザワクチンの注射タイプと鼻腔噴霧型では以下のような違いがあります。
注射タイプ: 不活化ワクチン
鼻腔噴霧型タイプ: 弱毒生ワクチン
弱毒生ワクチンはその名の通り、病原性を弱めた生きたウイルスを接種することになります。理論上、自然感染と同じ免疫反応が生じるため、高い免疫が得られると思いますが注射のタイプと比較しワクチン効果は同等のようです。わかりやすいように表にまとめてみます。
| 注射型ワクチン | 経鼻ワクチン (フルミスト ) | |
| ワクチンのタイプ | 不活化ワクチン | 弱毒生ワクチン |
| 投与方法 | 皮下注射 | 鼻スプレー |
| 対象年齢 | 生後6か月から | 2歳以上、19歳未満 |
| 痛み | あり | なし |
| 粘膜局所免疫 | 弱い | 強い |
| ワクチン効果持続期間 | 約4か月 | 約1年 |
フルミストの副作用
添付文書の記載内容では、フルミストで10%以上に認められた副反応は鼻閉・鼻漏(59.2%)、咳嗽、口腔咽頭痛、頭痛でした。10%未満ですが、発熱や下痢等も認められています。
フルミスト を接種できない方 (接種不適当者)
経鼻ワクチンは生ワクチンのため、一般的な不活化ワクチンの接種不適当者以外にも免疫不全、免疫抑制療法中の方、妊娠中の方は接種できません。
接種不適当者(予防接種を受けることが適当でない者)は以下のとおりです。
1. 明らかな発熱を呈している者
2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
3. 本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
4. 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する者及び免疫抑制をきたす治療を受けている者
5. 妊娠していることが明らかな者
6. 上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
フルミストの接種要注意者
添付文書の一部を抜粋し、簡潔に記載します
1. ゼラチンでアナフィラキシーを起こしたことがある者 (添加剤に精製ゼラチンが含まれています)
2. 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
3. 重度の喘息を有する者又は喘鳴の症状を呈する者
4. 本剤の成分又は鶏卵、鶏肉、その他鶏由来のものに対してアレルギーを呈するおそれのある者
フルミスト 併用注意薬剤
1. 抗インフルエンザウイルス剤 ワクチンウイルスの増殖が抑制され、効果が減弱する可能性があります。
2. サリチル酸系医薬品(アスピリン、サリチル酸ナトリウム等)、ジクロフェナクナトリウム、メフェナム酸
作用機序は不明ですが、サリチル酸系医薬品、ジクロフェナクナトリウム、メフェナム酸においては、ライ症候群やインフルエンザ脳炎・脳症の重症化との関連性を示す報告があります。
その他注意事項
1. ワクチンウイルスによる周囲への感染の可能性
ワクチン接種後に飛沫や接触により、周囲に感染 (水平伝播) する可能性がまれにみられたとの報告があります。したがって接種後1-2週間は重篤な免疫不全の方との接触は避けた方がよいでしょう。
よくある質問 (当院の見解も含めて)
1. 注射型ワクチンとフルミストを両方接種できますか?
→添付文書に記載がなく、有効性・安全性に関する情報はありません。両方接種は想定していないものと考えられので、当院は片方のみの接種を推奨します。
2. フルミストと他のワクチンとの接種間隔、同時接種について
→添付文書にはほかの予防接種との接種間隔・同時接種について記載がありませんが、同時接種は可能であり接種間隔も必要ありません (生ワクチン同士でも、フルミストは注射ワクチンではないため)
3. 鼻詰まりや、鼻汁が多いときにできますか?
→添付文書上の規定はありませんが、鼻詰まりがひどい場合は粘膜にワクチンが到達しづらくなる可能性があり、延期もしくは注射接種に切り替えることを検討してください。
4. フルミスト接種後にインフルエンザ迅速検査で陽性を示すことはありますか?
→接種後1週間ほどは陽性をしめすことがあるようです
5. 接種後に妊婦さんとの接触は避けたほうがよいでしょうか?
→接種後に水平伝播の可能性はまれにありますが、免疫不全状態でなければ妊婦さんとの接触を厳にさける必要はありません。
6. フルミスト接種でインフルエンザを発症することはありますか?
→あります。治験では2%ほどの頻度で発症がみられました。接種後2-8日後に発症したと報告されています。脳症、脳炎の報告はありません。
注射型ワクチンは4価から3価に変更
従来の注射型の不活化ワクチンについて、今シーズンの変更点があります。インフルエンザワクチンには株といって、ウイルスのタイプをいくつか含ませて接種するのですが、今シーズンは4種類 (4価といいます) から3種類 (3価) になります。A型 (H1N1, H3N2) 、B型 (ビクトリア系統、山形系統) の4価でしたが、B型の山形系統の流行はほとんどないため今シーズンはワクチン株の中から外れることになりました。
インフルエンザウイルスは変異しやすいウイルスなので、流行しそうな株に合わせて毎年ワクチンを作っています。流行しそうかどうかは世界中でウイルスの流行情報が収集され、世界保健機関 (WHO) が次シーズンのワクチン株として推奨、日本ではそれを元に国立感染症研究所が中心となりワクチン株を決定しています。
経鼻弱毒生ワクチン (フルミスト) のワクチン製造株は以下の通りです
A型株 A/ノルウェー/31694/2022 (H1N1) 、A/パース/722/2024(H3N2)
B型株 B/オーストリア/1359417/2021(ビクトリア系統)
注射型ワクチンのワクチン製造株は以下の通りです
A型株 A / ビクトリア / 4897 / 2022 (H1N1) 、A / パース / 722 / 2024 (H3N2)
B型株 B / オーストリア / 1359417 / 2021 (ビクトリア系統)
フルミストと注射型ワクチンとで若干のワクチン株の違いがありますが、いずれもWHO推奨の株でありワクチン効果に大きな影響を与えるものではないと考えます。
まとめ
・フルミストは痛みのないインフルエンザワクチンとして、お子様のインフルエンザ予防接種の新たな選択肢といえます
・注射ワクチンよりも、接種制限や副作用の問題 (ワクチンによるインフルエンザの発症) があります
・注射ワクチンと比較して予防効果に明確な差はありませんが、効果持続期間が注射ワクチンより長くなると考えられています
・費用面では注射1回の年齢相 (13歳以上) では、高額になります
フルミストの最大のメリットは痛みがないことなので、注射が苦手なお子様、痛みを感じたくない場合は検討していただければと思います